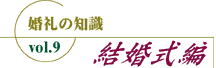 神前結婚式の流れ2 神前結婚式の流れ2 |
| 鈴の舞奉納
|
 |
ユウベルグループの結婚式場では、新郎新婦の今後の幸福を祈り、雅楽の音に合わせて巫女により鈴の舞の奉納を行っています。
鈴は、その音の清らかさから名付けられたとされ、日本でも古代から神事に用いられてきました。『古語拾遺(こごしゅうい)』でも、岩戸隠れした天照大神(あめのうずみのみこと)をなごませるため、天鈿女命が鈴のついた矛を持って舞ったと記されています。神社の拝殿の鈴、神楽の鈴は、神霊を招き邪霊を払うものとして、神と人を結ぶ重要な役割を担うと同時に、人の心をすがすがしくさせてくれるものです。
|
|
| 三盃の儀 |
 |
いわゆる三々九度の盃のことです。唐の国(今の中国)で二つに割ったひょうたんを使って夫婦が酒を飲んだのが日本に伝来したという説、応神天皇(五世紀)が、出会われた翌日に女性の家に行かれると、女性は天皇に御盃を捧げ歌を謡われたとあり、これがはじまりだとする説等があります。
新郎新婦、媒酌人が起立すると、巫女が三方にのせた三つ組の杯と雄蝶、雌蝶に飾られた銚子を持って、新郎の前に進みます。一番最初の杯(小杯)は、新郎から三口で飲み干し、さらに新婦、新郎の順に飲み干します。二番目の杯(中杯)は、新婦、新郎、新婦の順となります。三番目の杯(大杯)は、新郎、新婦、新郎の順となり、三盃の儀が終わります。お酒の飲めない人は、杯に口をつけるだけでかまいません。 |
|
| 玉串拝礼 |
 |
玉串とは、榊の枝に紙垂(しで:白紙を段状に切ったもの)がつけてあり、儀式の時に神前に供えるものです。本居宣長の説では、「手向串(たむけぐし)」の略とされ、また、古くには玉をつけたから玉串とする説もあります。そもそも玉串には、榊などの常盤木(常緑樹)の枝に木綿や麻をつけたものや、竹の串に鏡や玉をつけたものが使われていました。その後、鏡や玉は使われなくなり、木綿や麻のかわりに紙が使われるようになって、現在の形になりました。また、玉串の玉は霊にも通じます。自分の霊を込めて神に捧げ一心に祈ることで願いを神にとどけ、玉串を介して神と人が出会います。
結婚式では、最初に斎主が神前に玉串をささげて一拝し、次いで巫女が新郎新婦に玉串を渡します。新郎新婦は神前に進んで玉串をかかげ、一拝してから玉串を捧げます。供えたら、一歩下がって、二拝四拍手一拝してから席に戻ります。
一般には二拝二拍手一拝が基本ですが、伊勢神宮の八度拝・八開手や、出雲大社の四拍手の例もあります。ユウベルグループの結婚式場には出雲大社の神をお祀りしていますから、二拝四拍手一拝となっています。
|
|
| 誓詞(せいし) |
 |
新郎新婦が神前に進み、誓詞、いわゆる誓いの言葉を読み上げます。なお、誓詞はたいていの式場に用意されていますが、オリジナルのものを読む例もあります。
|
|
| 指輪交換の儀 |
 |
もともとは欧米の習慣ですが、今では神前結婚式にも取り入れられるのが一般的になりました。巫女が三方にのせて指輪を持ってきたら、最初に新郎が、新婦の左手薬指に指輪をはめ、次に新婦が、新郎の左手薬指に指輪をはめます。
|
|
| 親族盃の儀 |
 |
巫女が、両家の親族の杯に、上座から順に神酒を注ぎ、次いで新郎新婦、媒酌人夫妻に注ぎます。斎主の合図で一同起立し、神様とともにお神酒をいただき、神々と交流を深めながら、めでたい親族固めの式を行います。
|
|
| 参考文献/「神道辞典」(弘文堂)、「神道のしきたりと心得」(池田書店)、「神事の基礎知識」(講談社)、「いま、知っておきたい神さま神社祭祀」(主婦の友社) |
|
Copyright © 2000- UBL Group All rights reserved.
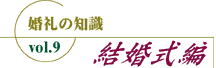 神前結婚式の流れ2
神前結婚式の流れ2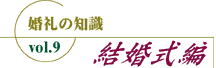 神前結婚式の流れ2
神前結婚式の流れ2