|
1--熨斗(のし) のしあわび、つまりあわびを延ばしたもので、不老長寿の薬とされています。進物に酒肴を添えるという古来のしきたりが、現代の熨斗に象徴的に残っています。熨斗は鶴の水引と共に贈ります。夫婦になると一生他の鶴とは添わないといわれる鶴は、千年の長寿と、愛情を表します。
2--寿栄広(すえひろ) 末広がりを表す白扇のことです。夫婦ともに末長く幸せに、という願いをこめて、一対で贈られます。亀の水引と共に贈りますが、急がず休まず、幸せを築き続けるという願いがこめられています。
3--御帯(おんおび) 昔は帯や小袖などが結納品の中心でした。現在では御帯料としてお金を包みます。いわゆる「結納金」といわれるものです。松の水引と共に贈られますが、松の葉は一年中緑であることから、長寿と永遠の若々しさを表します。
4--松魚(かつお) 鰹節のことです。“勝ち魚”ともいわれ、おめでたい儀式に使われる代表的な肴。魚料として2〜3万円を包みます。質実剛健、節度、潔白の意味をもつ、竹の水引とともに贈ります。
5--家内喜多留(やなぎだる) お酒を入れる柳の樽のことで、家の中に喜びごとが集まり、いつまでもとどまっているように、との願いがこめられています。また、酒は慶事や儀式ではつきもの。酒料として1〜2万円を包みます。春に先駆け花が咲き実を結び、忍耐の象徴とされる梅の水引とともに贈ります。
6--高砂(たかさご) 松の精とされ、松の木陰を掃き清める老夫婦の人形です。いつまでも仲良く添い遂げるようにという意味が込められています。
結納品以外には、目録(茂久録)、家紋の入ったふくさ、風呂敷、広蓋などを用意し、場合によっては家族書と親族書も用意します。
結納は、女性の自宅で受けるのが理想です。受ける側はふくさ、広蓋と受け書を用意し、儀式の後におもてなしの食事を用意します。最近では結納やその後の会食を、式場等でとり行なう人も増えています。
|
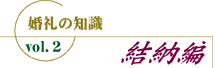 「現在の結納」
「現在の結納」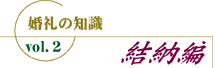 「現在の結納」
「現在の結納」