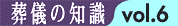 |
葬儀について
前回は通夜について述べ、ご遺体との夜を徹したお別れの儀式について説明させていただきました。今回からは葬儀についての起源や意義について述べて参ります。 |
|
葬儀の起源
 死者を葬る一連の儀礼を葬送儀礼と言い、私達は「葬儀」と略して呼んでいます。歴史的に見ると旧石器時代から、すでに遺体に対してなんらかの処置がなされた形跡が有り、遺体の処理は宗教の発生と共に古くから行われていたと推測されます。また、「葬」とは死体を草により上と下で覆うと書く事から、遺体を隠して見えなくする意味も含まれていると言われています。 死者を葬る一連の儀礼を葬送儀礼と言い、私達は「葬儀」と略して呼んでいます。歴史的に見ると旧石器時代から、すでに遺体に対してなんらかの処置がなされた形跡が有り、遺体の処理は宗教の発生と共に古くから行われていたと推測されます。また、「葬」とは死体を草により上と下で覆うと書く事から、遺体を隠して見えなくする意味も含まれていると言われています。
葬儀の変遷
葬儀の形式は基本的には、生者との別離であり、死者と生者の分離が主要なモチーフとなって、死者や死者の霊に対する態度が、民族の持つ世界観を反映して変遷してきました。原始・古代にあっては、死は超自然的な原因によるものとされ、死者は異常な状態ある危険なもの、汚れたものとされ、その霊は生者に対して害をなす恐ろしいものと考えられていた様です。
現在の民間宗教でも、別家、別火して死の穢れを避け、葬儀の終わりには塩をまいて浄めるなどの風習が残っています。これは、死者や関連の深い人々を隔離し死を恐れたことのあらわれです。また葬儀に関して行われる所作が平常の時と違い、逆屏風にしたりする習慣などは、全て死霊への恐怖から来ているものと考えられています。
現在の葬儀感
葬儀は死霊に対する恐怖心が大きく影響していると述べましたが、一方、死者に対する追慕や感謝の感情が強く交錯することを見逃す事はできません。現在でもお通夜は、夜を撤して在りし日の故人を偲んだり、多くの情をいただいた事に感謝したり、特に親族の思いは魂が蘇ってほしいという願望が最も強くあらわれます。現在では、死霊への恐怖心は薄れ、故人の死を悼み、冥福を祈ることが葬儀の意義とされていますが、悲嘆に暮れる遺族に、多くの人々が駆けつけ慰めの言葉をかけてくれるこの儀式は、人間にとって美しい風習であると言えます。
|
|
|
《参考文献》
「仏教儀礼辞典」藤井正雄編
「仏教学辞典」法蔵館刊
「仏教大辞典」古田紹欽・金岡秀友・鎌田茂雄・藤井正雄監修
「浄土真宗のおつとめ心得」浄土真宗本願寺派東京教区青年僧侶協議会監修
|
Copyright © 2000- UBL Group All rights reserved.