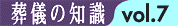 |
会葬について
故人の死を悼み、冥福を祈ることが葬儀の大きな意義のひとつです。
また悲嘆にくれる遺族に、多くの人々が駆けつけ、慰めの言葉をかけてくれるこの儀式は、日本的な美しい風習でもあります。今回は会葬について述べてみましょう。 |
|
会 葬
葬儀式・告別式に参列することを会葬といいます。会葬のマナーとしてまず服装ですが、故人に対する弔意の表徴であることを考えれば、正式な喪服で弔問するのが望ましいと思われます。喪服の持ち合わせのない場合は、借りることもできます。男性の場合は黒のダブル、女性の場合は肌の露出しない黒のワンピースかスーツでもかまいません。帳場に着いたなら、香典を差し出し、会葬者記帳簿に記入し開式の時間を待ちます。
喪 服
喪服は元来、喪屋にこもる服装で、喪に服していることを示し、葬送後の一定期間その服装を続けねばなりませんでした。本来は棺に巻いていた白木綿を帯びにしたとか、縄帯を締めるとか、散らし髪にし髭を剃らないなどの風習もあったようですが、現在その服装は近親者や、さらに広くは会葬者の服装まで意味するように変わってきました。
喪章は喪服の簡略化されたもので、服の左腕に黒い布片を巻き付けたり、黒白のリボンを胸につけたりします。従って正式の喪服の上に喪章を巻く必要はありません。
香 典
葬儀に際し、故人の霊前に捧げ供える金銭・物品を香典といい、香資・香典ともいいます。香典は本来「香奠」と書き、語義からいえば「奠」は薦めること、供えることを意味する語で、香を供えること、あるいは香を薫じて供えることをいいます。そして現在使われている「香典」の文字の「典」はものを買い取る意味があるので、香を買う代物または金銭として差し出すことを意味し、喪家や故人との交際に従い贈られるものとなっています。従来は米を主としていましたが、今日では金銭に変わり、相互扶助の機能や、故人に、何らかの形で最後の感謝の気持ちを表す役割を持っているようです。
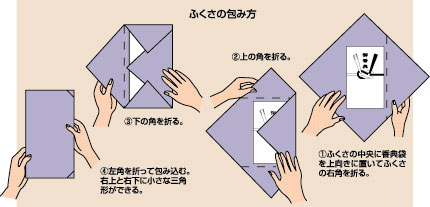 |
|
|
《参考文献》
「仏教大辞典」古田紹欽・金岡秀友・鎌田茂雄・藤井正雄監修
「仏教儀礼辞典」藤井正雄編
|
Copyright © 2000- UBL Group All rights reserved.